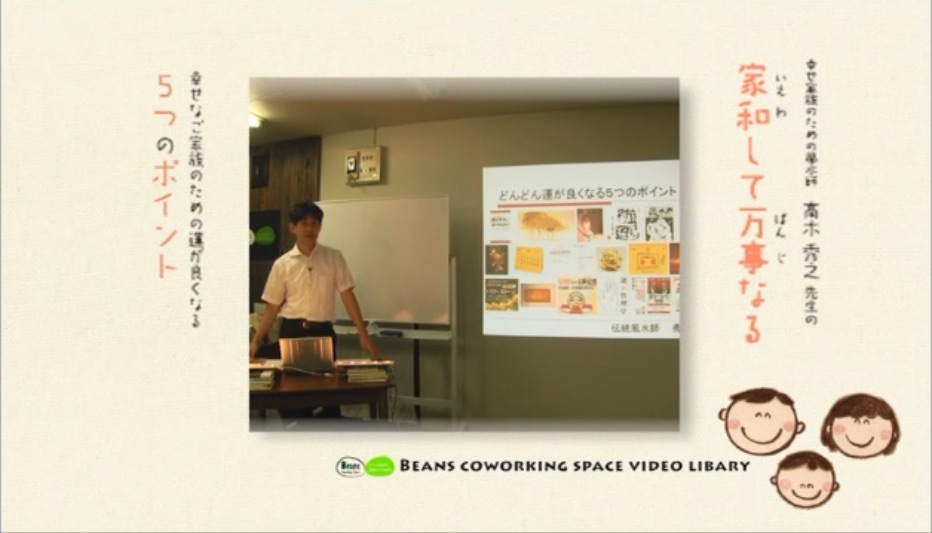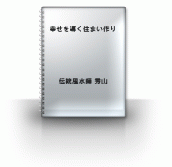式年遷宮とは、神宮の社(2つ敷地もあります)を隣の社へ20年ごとに、移す行事のことですが、その意義はwikipediaによると
・建物の「清浄さ」を保つ限度が、20年程度であるため。とあります。
・建替えの技術を伝えるためには、宮大工の寿命や実働年数から考えて、20年が適当。
・旧暦の11月1日が冬至にあたるのが、19から20年に一度の周期であるため。
・一世代がおよそ20年であるため。
・神嘗祭(かんなめさい)に供される穀物の保存年限が20年であるため。
なるほど、神道としての意義と、実際に祭祀を行う もろもろの事情の限界、という感じですね。
じつは20年というサイクルは、風水の暦に共通するサイクルなのです。
三元派では、三元九運(さんげんきゅううん)という20年ごとの周期を3回ずつ、つまり60年を一元として
三元とは上元、中元、下元の三つで、それぞれ干支が1巡する60年です。
また九つの運はそれぞれ20年で180年を一サイクルと考えます。
立て替え前の社は、この三元九運の七運(1984年~2003年)に遷宮されました。
最近遷宮がおこなわれたのが、八運の20年間のちょうど真ん中の年、2013年です。
当然次の遷宮は20年後の2033年ということになります。
このように、20年の真ん中で立て替えるという、風水の技法も存在しています。
七運と、八運、九運では、方位の吉凶が変化します。
しかし、この20年の真ん中で立て替える続けることで、ずっと どの運の吉凶方位にも対応した建物となるという技術です。
偶然の一致と考えるには、あまりにもタイミングがぴったりすぎます。
飛鳥時代の天武天皇の時代から1300年続いている、この遷宮行事に実はかくされた風水の技法があった!
と考えるのは、ちょっと深読みしすぎかもしれません。
パワースポットについての関連記事はこちらから
伝統風水師秀山