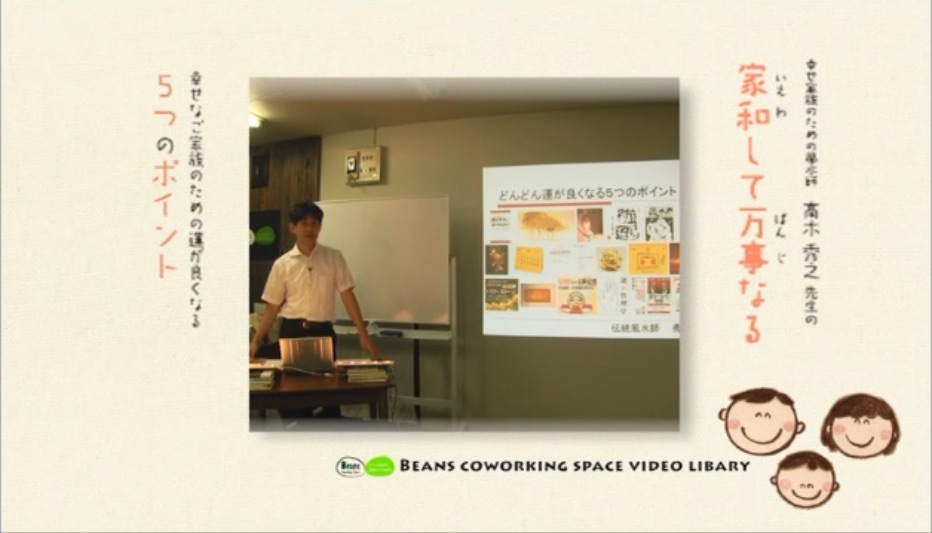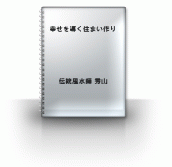これは四柱推命の神殺(しんさつ)の一つである「驛馬(えきば)」に関する考え方から来ています。
吉日選び(擇日/たくじつ)で結婚の日取りを決めるときには、単に「暦で大安を探す」だけではなく、じつに細かい条件を考慮します。
とくに昔は、女性側の宿命を念入りに調べることが多く、「良い嫁になるかどうか」を判断するためにこの神殺を確認する習慣がありました。
では驛馬(えきば)とは?なにかというと
驛馬は文字通り「馬」を表し、もともとは「旅に出る」「移動する」「落ち着かない」といった意味があります。
そのため「行動的」「自由」「忙しい」といった性格を示すと解釈されます。
昔の社会では「嫁には家を守ってもらいたい」という価値観が強かったため、自由奔放な性格は「結婚には向かない」と見られてしまったのです。
驛馬の出し方ですが、生まれた年や生まれた日の十二支から割り出すことができます。
(例:子=寅、丑=亥、寅=申、卯=巳 … というように、それぞれに対応する支が決まっています。以下をごらんください)

ただし、驛馬を持っているからといって「結婚に不向き」と決めつけるのは早計です。
四柱推命では、驛馬がその人にとって良い五行に属していれば、むしろプラスに働くこともあります。
さらに「正官」を持っている人であれば、その真面目さや自律性が自由さをコントロールしてくれるため、安定した結婚生活につながると考えられます。
このように、結婚式の日取りを決める際には、ただ吉日カレンダーを見ればいいというものではなく、その人の宿命まで考慮する必要があります。
つまり「方位の風水」と「四柱推命」を両方合わせて判断するのが本来の擇日なのです。
結婚は人生において大きな節目ですから、昔の人がとことん細かく見ていたのも納得ですね。
もちろん現代では昔の価値観をそのまま当てはめるわけにはいきませんが、「自分の性質を理解したうえで日を選ぶ」という考え方は、今でも十分に役立ちます。
冒頭に書いた「馬がつく女性は自由すぎる」というのは、昔の価値観を反映した一つの見方にすぎません。
驛馬があっても、五行のバランスや正官の有無によって意味合いは変わります。
結婚の日取りを決めるときには、自分や相手の宿命までしっかり見て判断すると、安心して未来を歩んでいけると思うのです。
伝統風水師秀山