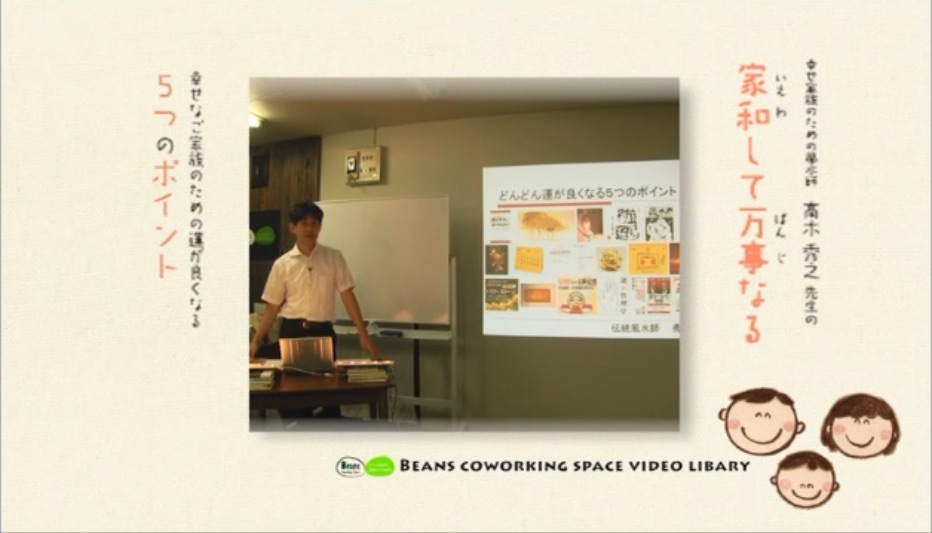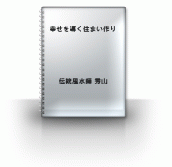これは、結婚式・引っ越し・契約・開業・お墓の建立など、人生の節目に関わる大切な日にちを決めるための技法です。
擇日では、西暦ではなく 旧暦(農暦)を用います。
農暦は月の満ち欠けを基準にした暦で、日本でも「十五夜」といえば満月の夜をイメージしますよね。
ところが実際には、十五夜が必ずしも満月とは限らないのです。
月の運行は規則的でありながら微妙なズレがあり、その差が旧暦と現代の天文学的な満月に違いを生み出します。

ここで大切になってくるのが、月齢に基づいた吉凶判断です。
擇日(二十八宿)では 朔(さく)・弦(げん)・望(ぼう)という三つのタイミングを特に重視します。
・朔(新月):旧暦1日、太陽と月の位置が重なり光景差が0度の時。
・上弦:太陽と月の角度が90度になる日(およそ7日目)。
・望(満月):80度に開いた時で、いわゆる満月。
・下弦:270度の角度、月が再び欠けていく時期。
この中で、多くの方が「満月=最強の開運日」と思いがちなのですが、実は擇日的にはそうとは限りません。
むしろ、満月(望)の日は感情やエネルギーが過剰になりやすく、結婚や契約ごとにはあまりふさわしくないとされます。
実際、統計的にも満月の日は犯罪率が上がるという研究があるほど。
さらに手術や治療の開始も望の日は避けたほうが無難です。
一方、新月(朔)も注意が必要です。
月が隠れて見えないこの日は、嫁入り・宴会・旅行・出世祝いなど、華やかな行事には凶とされます。
つまり「新月こそ新しいことを始めるのに最適!」という一般的なスピリチュアル解釈とは、まったく逆の意味合いを持つのです。
こうして見ると、「満月=吉」「新月=開運」という世間のイメージに安易に乗ってしまうと、むしろ逆効果になる可能性があります。
擇日の考え方では、自然界のエネルギーは「強ければ良い」ではなく、「調和しているかどうか」が大切だからです。
ですから、引っ越しや結婚など大きなイベントを計画する時には、大安などの六曜や九星暦などで決めるのではなく、正しく擇日を用いることが重要です。
伝統風水の擇日は単なる占いではなく、長い歴史の中で培われた「自然と調和するための智慧」であり、時間と方位のエネルギーを上手に活用する方法なのです。
伝統風水師秀山公式HP